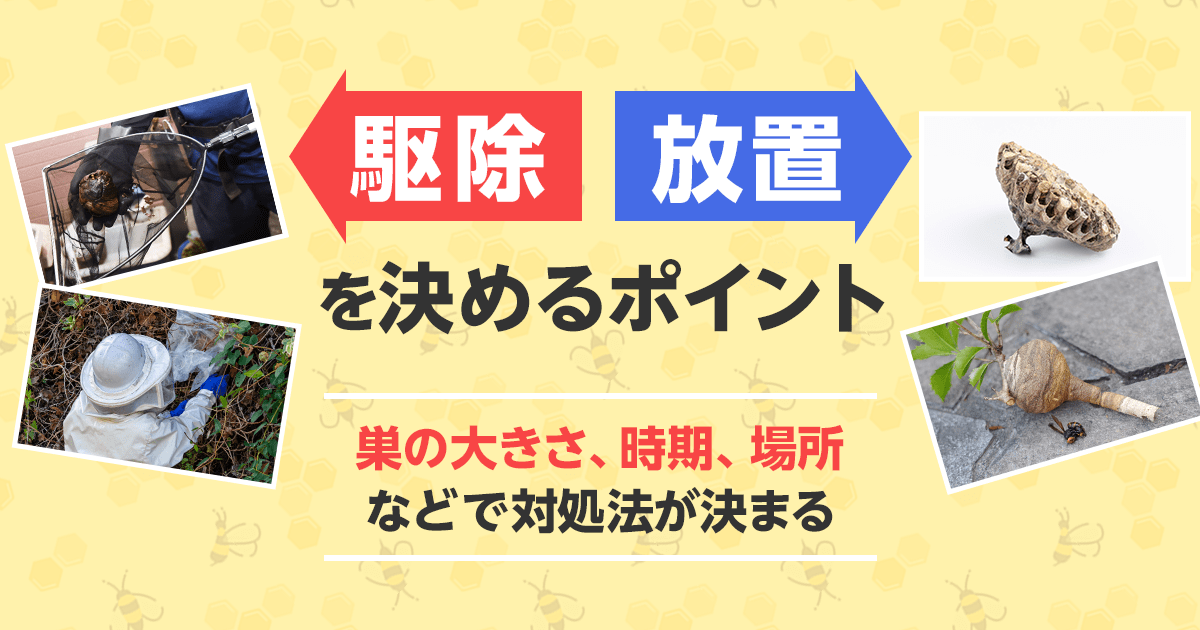自宅の周辺にできた蜂の巣をどうにかしたい場合は、正しい対処法を知っておく必要があります。これは、正しい対処法を知らずに蜂の巣を放置または駆除すると、蜂に刺されてしまう危険性が高まるためです。
このコラムでは、蜂の巣の対処法について解説していくので、正しい対処法を把握した上で蜂の巣に対処しましょう。
目次
蜂の巣は放置しても大丈夫?
結論からいうと蜂の巣を放置するのはとても危険なので、なるべく早めに駆除をおこなうことをおすすめします。しかし、中には放置できるケースもあります。ここでは、蜂の巣を放置できるケースと蜂の種類について解説していきます。
アシナガバチ/スズメバチの巣は放置できるケースがある
基本的に、蜂の巣は見つけ次第駆除した方がよいですが「アシナガバチ」と「スズメバチ」の巣は特定のケースに限り放置できることがあります。特定のケースとは「もう少しで冬になる」かつ「巣が人通りの少ない場所にある」状況です。これは、アシナガバチとスズメバチのライフサイクルが関係しています。
一般的に蜂は、卵を産んで数を増やす役割を担う「女王蜂」とエサ集め/幼虫の世話/外敵の排除/巣の拡張などの役割を担う「働き蜂」の二種類に分けられます。このうち、人を積極的に攻撃してくるのが働き蜂です。
攻撃性が高くて危険な働き蜂ですが、アシナガバチとスズメバチの働き蜂は冬が来ると寒さで死滅してしまいます。そして、残った女王蜂も巣を捨てて単身で越冬をおこなうため、冬は巣の中に蜂がいない状態になるのです。このことから、冬間近のアシナガバチ/スズメバチの巣に限り、放置で対処するのもひとつの手といえます。
アシナガバチの巣の特徴や駆除方法はこちらをご覧ください。
あわせて読みたい
ハチの種類と特徴について

アシナガバチとスズメバチの巣は冬になるともぬけの殻となりますが、同じく蜂の仲間であるミツバチは女王蜂と働き蜂が共に巣の中で越冬します。そのため、いくら放置していてもいなくなるようなことは基本的にありません。
このように蜂ごとに特徴が異なるため、どの蜂の巣であるかをしっかり把握した上で正しい対処をおこなう必要があります。ここでは、蜂の種類ごとの特徴について解説していくので、蜂を見分ける際の参考にしてみてください。
【スズメバチ】
・特徴
オレンジがかった黄色と黒の縞模様。
まっすぐすばやく飛ぶ。
・巣の見た目
茶色/白色/ベージュ色などが混ざり合ったマーブル模様の外皮がある球状。
【アシナガバチ】
・特徴
明るい黄色と黒の縞模様。
ふらふらと飛び回る。
全体的にスリムな体型。
・巣の見た目
白色または灰色で枯れた蓮を逆さにしたような見た目。
【ミツバチ】
・特徴
小柄でずんぐりむっくりな体型。
後ろ足に黄色い塊(花粉団子)が付着している。
・巣の見た目
黄色で板状の巣が何枚も重なり合って複数の層を形成している見た目。
蜂の巣は自分で駆除できる?
蜂の巣の駆除は一歩間違えると大ケガをする危険性があるため、可能な限り業者に駆除を依頼することをおすすめします。しかし、中には「自分で駆除したい」と考える方もいることでしょう。そこで、ここでは「自分で蜂の巣を駆除できるかどうかの基準」と「自分で駆除する方法」について解説していきます。
自分で駆除できる基準
自分で蜂の巣を駆除できるかどうかは「蜂の種類」「巣がある場所」「巣の大きさ」次第です。自分でも駆除をおこなえるケースは次のとおりです。
・巣がアシナガバチまたはミツバチのものである。
スズメバチはプロでも駆除に手こずることがあるほど危険度が高いため、素人は手出し厳禁です。
・巣が駆除しやすい場所にある。
巣が高所や閉所にあると駆除がうまくできなかったり、駆除の際にケガをする危険性が高まったりします。
・営巣初期段階の小さな巣である。
スズメバチに比べて危険度の低いアシナガバチやミツバチであっても、巣が大きくなるとそれに比例して蜂の数が多くなり安全な駆除が難しくなります。
・蜂が活発になる時期以外である。
アシナガバチは7~9月、ミツバチは10~11月と2~3月に活発になって危険度が高まるため、この時期は駆除を避けましょう。
・蜂駆除用の防護服を用意できる。
蜂に刺されると毒性の強さにかかわらずに、アナフィラキシーショックを引き起こして最悪命を落とす危険性があります。厚手の服やレインコートなどで代用しようとせず、しっかりと防護服を用意した上で駆除に挑むようにしましょう。
自分で駆除する方法
自分で蜂の巣を駆除する場合は次のものを用意しましょう。
【用意するもの】

・蜂駆除用の防護服
蜂駆除用品の通販などで購入可能です。また、市によっては貸し出しをしているケースもあります。
・蜂用の殺虫剤
薬局やホームセンターなどで可能です。駆除作業中に切れしてしまわないように、多めに用意することをおすすめします。
・懐中電灯
多くの蜂は昼行性であり、日が暮れると巣にこもります。そのため、日暮れ以降に駆除をおこなえば、駆除漏れと蜂に攻撃されるリスクを減らすことができます。
・赤いセロハン
蜂は光に向かって飛ぶという性質があるため、暗闇の中でそのまま懐中電灯を使うのは非常に危険です。蜂は赤い光をうまく視認できないため、赤いセロハンを懐中電灯に貼り付けて光を赤色にすることで、こちらに向かってくるリスクを抑えることができます。
・ゴミ袋
駆除した蜂の巣や死骸を処分するために必要です。市や自治体によっても異なりますが、巣や死骸は可燃ゴミとして取り扱われることが多いです。
【駆除の手順】
1.明るいうちに巣の場所を確認しておく。このときに、蜂を刺激して刺されてしまわないように注意してください。
2.日が暮れてから懐中電灯で巣の位置を確認しつつ、少し離れた位置から殺虫剤を吹きかける。
3.巣から蜂が飛び出してくるので、しばらく殺虫剤を吹きかけ続ける。
4.飛び出してくる蜂が少なくなってきたら、殺虫剤を吹きかけつつ巣との距離を詰める。完全に蜂の羽音が消えるまで続けてください、
5.駆除が完了したら蜂の巣撤去し、死骸と一緒にゴミ袋に入れる。蜂の針が袋から貫通しないように、袋は二重にすることをおすすめします。
6.市/自治体のルールに従って巣と死骸を処分する。
蜂の巣は再発するケースがある
蜂の巣を駆除したあとに、時折駆除漏れした蜂が元々巣のあった場所に戻ってくるケースがあります。このような、蜂が巣のあった場所に戻ってくる現象のことを「戻り蜂」といいます。多くの場合、戻り蜂が発生してもしばらくすれば蜂は諦めて去っていきますが、中には再度同じ場所に巣を作りはじめることがあるのです。
ここでは蜂の巣の再発を予防する方法をいくつかご紹介していくので、蜂の巣駆除をおこなったあとに実施してみてください。
蜂の巣の予防方法

・周りの草木を剪定する
蜂は基本的に風雨をしのげる場所に好んで巣を作ります。そのため、生い茂った草木は蜂にとって格好の営巣場所になってしまいます。そのため、成長し過ぎた草木はしっかり剪定して、蜂が巣を作りにくい環境にしましょう。
・蜂の忌避剤を散布する
巣があった場所に忌避剤を散布しておくことによって、蜂が近寄ってくるのを防ぐことができます。忌避剤は市販のものを利用するほか、木酢液を水で薄めて霧吹きで散布することでも代用可能です。
殺虫剤と異なり、忌避剤には殺虫成分が含まれていないため、戻って来た蜂に吹きかけて蜂を怒らせてしまわないように注意してください。
・香りの強い洗剤や柔軟剤を避ける
蜂は甘い香りを好むため、洗剤や柔軟剤に使用されている香料に引き寄せられやすいです。そのため、庭やベランダなどで洗濯物を干す際は香りの強い洗剤や柔軟剤は避け、蜂を引き寄せないようにしましょう。
まとめ
蜂の巣は多くの場合、放置すればするほど巣が大きくなって駆除の危険度が増すため、見つけ次第駆除することをおすすめします。自分で駆除をすることも可能ですが、準備が大変な上に刺される危険も伴うため、可能な限り業者に駆除を依頼してください。
蜂の巣でお困りの際は弊社の相談窓口にお電話ください。弊社では、蜂の巣駆除だけでなく再発予防までできる業者もご紹介しています。プロに任せて安全に蜂の巣を駆除しましょう。
ハチの被害を迅速に解決!
到着までにかかる時間 最短10分
※対応エリアや加盟店によって変わります
お家の近くにハチの巣がある状態は大変危険です。ご家族や、ご近所の方に被害が出る可能性があります。危険なハチはプロに依頼して素早く、安全で確実に駆除を!
- 『生活110番』では、
お住いの地域で人気のプロを探せます - スズメバチ・アシナガバチ・ミツバチ、あらゆるハチ駆除をお任せください。
-
- 蜂の巣駆除
- 8,800円~
蜂の巣駆除業者を検索
厳選した全国の蜂の巣駆除業者を探せます!