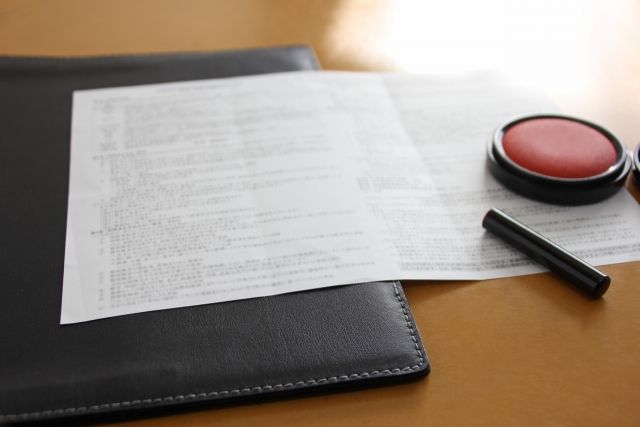
建物を建てたときに法律関係を明確化させるための登記が必要なのはよく知られていますが、建物を解体したときにも滅失登記が必要になることをご存知ですか?
滅失登記を忘れると、行政罰を科されたり土地が売れなくなったりと、あとで困ることが続出します。
解体工事の上で意外な盲点になりやすい滅失登記について解説します。
目次
解体工事に欠かせない『滅失登記』とは?
建物や家屋を解体したときは、1か月以内に不動産登記法に基づいて登記簿を閉鎖する手続きが必要になります。この手続きのことを建物滅失登記といいます。(以下、「滅失登記」とします)
建物を建てた際に登記した場合は解体したときに滅失登記を行うことが法律によって義務付けられています。
登記といわれれば行政書士や司法書士の資格や知識が必要かのように思われがちですが、滅失登記に限っていえば、ご自身でも手続きができる比較的簡単な登記といわれています。そのため、費用を抑えるために自分で滅失登記する人も多くなっています。
それでも、もちろん滅失登記には法律の知識は必要になるので、自分で登記することに不安がある場合は土地家屋調査士にお任せすることをおすすめします。
地域や条件によって変わりますが、滅失登記にかかる費用はおおむね4~8万円前後になります。
滅失登記が完了すると登記所から市区町村などの自治体へ連絡が行き、固定資産税に反映される仕組みになっています。
そのため、滅失登記は建物の権利関係を示すためだけでなく、税の把握のためにも重要な役割を果たすといえます。

滅失登記をしないとどうなる?
わざわざ建物や家屋を解体することには「新築を建てる」「更地で売却する」「土地を貸し出す」などさまざまな目的があることでしょう。
しかし、そのために滅失登記をしていないことは、今はよくても将来にわたって多くの問題を生じます。具体的には、以下のような問題が発生することがあるので注意しましょう。
行政罰を科される
滅失登記は必ずしもしなければならないものではありませんが、滅失登記は法律上の申請義務になっているため、申請を怠った場合は10万円以下の過料を科されることがあります。
滅失登記をすべき期間は建物が滅失した日から起算して1か月以内となっています。
実際に、過料を徴収されるケースは少ないようですが、全くないとは言い切れないので注意が必要です。
存在しない建物の固定資産税を徴収され続ける
滅失登記を行わずに放置しておくと市役所が建物の滅失に気づくまで税額が変わることはありません。
本来であれば、建物にのみ固定資産税がかかり、宅地の固定資産税は減免されている仕組みになっていますが、滅失登記を怠るこのような恩恵を受けることができなくなります。
つまり、存在しない建物の固定資産税を納め続けることになるので、経済的に大きな損失を被ることになるのです。

土地の売買ができなくなる
そもそも登記には、その土地の所有者を明確にするという役割があります。
しかし、滅失登記がなければ現状と登記との間でずれが生じることになります。
一般的な不動産価格が安価ではない昨今、そのようなうさん臭い土地をわざわざ買い受ける人はほとんどいないでしょう。
もし土地を売買できたとしても、買主が建物を建築できなかったり建て替えできなかったりと新たなトラブルを生じる恐れもあります。
金融機関からの融資が受けられなくなる
住宅ローンを利用する場合、登記がなければ銀行などの金融機関の融資が受けられなくなってしまいます。それは融資したお金の担保とするものがなくなってしまう(抵当権の設定ができない)からです。
滅失登記に関してもそれは例外ではなく、金融機関から融資を受けたい場合は必ず登記しなければなりません。
建物の建築許可が下りなくなる
建物を建築するときには、事前に市区町村役場が建築確認を行うように申請する必要があります。しかし、そこに解体されたはずの建物が存在するという登記があると、建築許可が下りないこともあるのです。

滅失登記に必要な書類
自分で滅失登記をする際に、必要な書類は大きく6つあります。
登記申請書
登記所のホームページから一定の様式のものをダウンロードし、ワープロで登記事項証明書に記載されている不動産番号、所在、家屋番号、種類、構造、床面積などの必要事項を入力します。手書きでも構いませんが、その場合はボールペンを使って丁寧な字で書きます。
案内図
解体した建物がどの場所にあったか、どのような形をしていたかを示す建物の図面が必要です。これも登記所のホームページや郵送から手に入れることができます。
建物滅失証明書
記入した建物滅失証明書を解体業者に送って、解体した業者から印鑑を押して送り返してもらいます。
取り壊した会社の登記事項証明書
解体業者が正当な資格や許可をもって解体作業を行ったことを証明するために使います。解体した業者からもらいましょう。
取り壊した会社の印鑑証明書
建物滅失証明書に押印された印鑑が本物であることを証明するために使います。
解体した業者からもらうことができます。
原本付還付請求書
原本還付が必要な情報があれば、申請書と合わせて提出します。原本還付が可能かどうかは最寄りの法務局や地方法務局に問い合わせましょう。
そのほかには、必須ではありませんが、建物が滅失したことを証明する写真や代理人が行った場合に必要になる代理権限証明書など、状況に合わせてほかの書類も用意します。
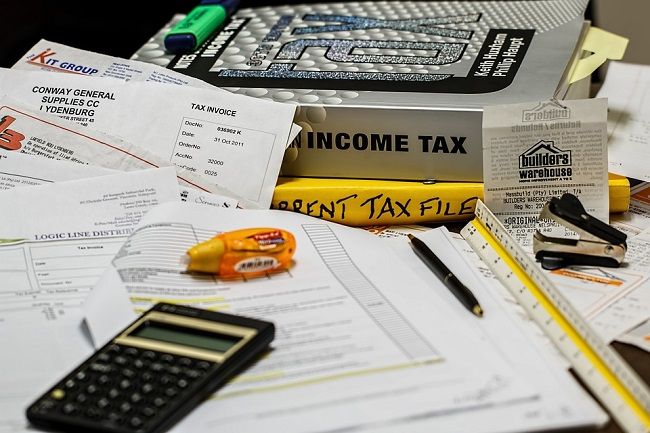
滅失登記の手順
個人や建物の状況によって多少異なりますが、滅失登記の大まかな流れは次のようになります。
登記簿の特定
まず、解体する建物の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、不動産番号、所在、家屋番号、種類、構造、床面積などの登記内容を確認します。
登記申請書の作成
次に、登記事項証明書(登記簿謄本)の内容をもとに、登記所に提出する登記申請書を作成します。
申請者は原則、建物の所有者か、もしくは共有名義の共有者の一人になります。
ただし、土地家屋調査士が代理することもできます。
この際、登記申請書のコピーを取っておいて控えにするとなおよいでしょう。
解体業者からの書類を入手
それと並行して、取り壊しを行った業者から建物滅失証明書・取り壊した会社の登記事項証明書・取り壊した会社の印鑑証明書という3つの書類を受け取ります。
必要書類の提出
そして、必要書類をすべて揃え、その建物が属する管轄の登記所に提出したら登記完了証を受け取りましょう。
申請からこの完了証を受け取るのにかかる期間はおおむね1週間程度です。ここまでできれば、無事に滅失登記が完了します。

滅失登記を依頼する場合
滅失登記が比較的簡単な登記であるとはいえ、法律的な知識がない人にとっては自分で登記するのは難しいものです。そこで、滅失登記を依頼する場合の注意点についてご説明します。
誰に依頼する?
滅失登記を依頼するときは、なるべく土地家屋調査士に直接依頼しましょう。
「登記といえば司法書士」というイメージがありますが、司法書士は法律上、滅失登記ができません。
不動産の登記には大きく2つあり、それは「権利に関係する登記」と「表題に関係する登記(不動産の表題登記)」です。
「権利に関係する登記」とは、不動産の権利の保存、設定、移転、消滅などを公示するための登記です。それに対し、「表題に関係する登記」とは土地の地番や建物の家屋番号を付すためのもので、これには建物滅失登記も含まれますが、原則土地家屋調査士のみが「表題に関する登記」の代理人となることができるのです。
司法書士に間違って滅失登記の依頼をしても引き受けてくれることはありますが、その場合は、あくまで司法書士は窓口になってくれるだけで、実際の滅失登記の作業は行いません。それどころか、司法書士の相談料を請求されて、結果として割高になることもあるので注意しなければなりません。
どうやって依頼する?
土地家屋調査士は不動産を所有している人ならともかく、一般の人にはあまりなじみのない職業かもしれません。
そのため、滅失登記の依頼をするためには土地家屋調査士によく関連している不動産会社や建設業に尋ねることが必要です。
また、建物の解体業者自身が滅失登記の依頼を引き受けて、土地家屋調査士にバトンタッチすることもあるようです。
身近な建設業、不動産会社、リフォーム業者、解体業者に確認してみましょう。
お金はいくらかかる?
自分で滅失登記を行う場合にかかる費用は、建物の登記情報を調べるのにかかる費用(おおむね1,000円程度)と法務局までの交通費、申請書類を郵送するときにかかる郵送費程度です。ちなみに、滅失登記には登録免許税はかからないので必要ありません。
それに対し、土地家屋調査士に依頼した場合はおおむね4~8万円前後の費用がかかります。一般の家屋であれば4~5万円で済むことが多いですが、建物の規模が大きく、棟数が多くなればなるほど費用も大きくなるからです。

こんな事例はどうすればいい?
不動産の登記は複雑なことが多く、一筋縄でいかないケースも少なくありません。ここでは、滅失登記をするときにありがちな困ったケースについてご紹介します。
未登記の物件を解体する場合
一般的に建物を新築したときは建物表示登記をしますが、登記がされていない物件も珍しくありません。とくに一昔前の古い物件は未登記であることが多くあります。
たとえば、金融機関などからとくに融資を受けない場合は抵当権設定登記が必要ないため、登記しないこともあります。
これは現在ではなかなか見られない事例ですが、一昔前のように金融機関の助けを得ずに自己資金のみで建物を建てることが珍しくない時代の物件ではいまだに未登記のものが多く存在します。
未登記の物件かどうか確認するためには、登記所で登記事項証明書のひとつである全部事項証明書が取れるかどうか確認します。そして、取れない場合は未登記の物件になります。
しかし、未登記の物件であっても市区町村が調査を行うので、固定資産税は課税されています。未登記の物件の所有者と判断された人物のもとには納税通知書が送付され、固定資産税が徴収されるのです。よって、そのまま未登記の物件を解体してしまうと、固定資産税が正しい形で徴収されなくなってしまいます。
未登記の物件に対しては登記そのものがないので、滅失登記をすることができません。そこで、家屋滅失届出書を提出する特別な手続きが必要になります。
家屋滅失届出書は市区町村などのホームページからダウンロードすることができ、解体業者に署名・捺印してもらってから提出します。詳しい提出先については市区町村ごとに変わってくるので、資産税課や税務課など税金にかかわる部署に問い合わせましょう。

土地の前所有者が滅失登記しなかった場合
土地の前所有者が滅失登記についての知識がなく、建物の解体だけを行ってしまうことで滅失登記をしていないこともよくあることです。
滅失登記忘れの土地を売買してしまった場合は買主から滅失登記を請求されることもあります。前述のように、滅失登記がされていなければ建物の立て替えや建築許可が下りないこともあるからです。
そのうえ、建物が立っていない土地は一見建物をすぐに立てられる土地に見えるので、買主も当然そういうものとして土地を購入し、あとでやっぱり建物が建てられないとなると損害を生じるおそれもあります。
滅失登記には解体業者が作成する書類もいくつか必要になりますが、年月が経てば建物の解体業者が提出すべき証明書や印鑑が入手できなくなります。
そうなると、土地家屋調査士への依頼が必要になり、その分の費用が必要になります。
土地の売主となる人も買主となる人も、滅失登記忘れの不動産には注意しなければなりません。

まとめ
滅失登記は必ずしも強制ではありませんが、税金の過剰な徴収や売買できないなどの不必要なトラブルや行政罰を受けることを考えると、なるべく早く確実に行うに越したことはありません。解体工事の際は忘れずに行いましょう。
不動産にはさまざまケースがあり、多くの法律の規則がつきものなので、一般の人では理解が難しく、どうにもできないことも多くあります。
しかし、だからこそ建物や家屋の解体をする場合は法律にも注意を払って行うとともに、困った際は業者とも相談しましょう。きっと素晴らしい解決策を教えてくれることでしょう。
解体工事を依頼できる業者や料金
依頼できる業者や料金について、詳しくは「生活110番」の「解体工事」をご覧ください。
他社との相見積もり歓迎!
最短1日で業者をご紹介!
※対応エリアや加盟店によって変わります
木造、鉄筋鉄骨などのさまざまな構造の建物の解体工事に対応しています。また解体工事中に出た古い家具の処分なども行いますので、安心してお任せください。
- 『生活110番』では、
お住いの地域で人気のプロを探せます - 塀や壁の除去といった一部だけの解体も請け負っています。
-
- 解体工事
- 1坪 19,800円~
解体工事業者を検索
厳選した全国の解体工事業者を探せます!

